様々なジャンルで活用されるケースが増加しているNFT。
今回は、その中でもトークンを活用したブランディング強化として、「日本酒×NFT」という領域で実証実験を行ったTIS株式会社の村上さんと、共同事業者である合同会社SAKEXの小松さんに取り組みに関しての内容や企画推進時の裏話を伺いました。
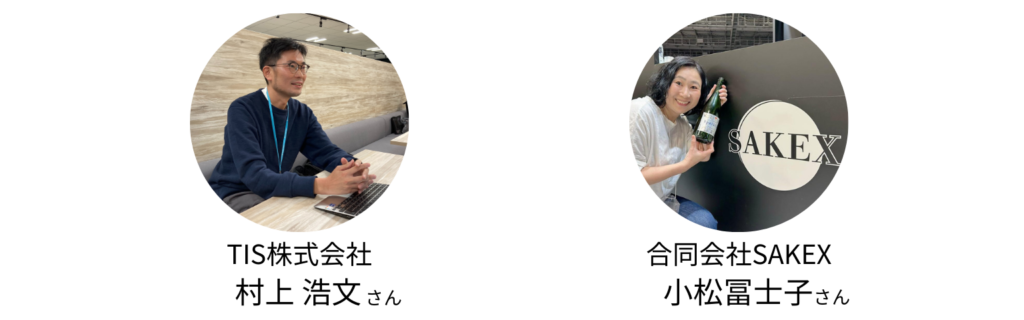
トークンを活用して日本酒ブランドのロイヤリティ向上目指す
ーーー(編集部)本日はよろしくお願いします。まずはSAKEX&米鶴酒造との取り組みについて教えて下さい

 TIS村上さん
TIS村上さんよろしくお願いします!
今回の取り組みでは当社TIS株式会社とSAKEXさん、そして米鶴酒造さんが連携し、日本酒と特別な体験を組み合わせた新しい取り組みを実施しています。具体的には、SAKEXさんのECサイト上にて、日本酒と特別体験チケットNFTをセット販売し、購入者にはまず米鶴酒造さんから日本酒を自宅にお届けしています。
その後、購入者は山形県高畠町で開催される特別イベントにNFTチケットを使って参加いただけるようになっています。また、現地にいらした方には「ファン証明トークン」を発行し、今後も酒蔵とのつながりを深められる工夫をしています。



この取り組みは、当社TISによる「トークン活用型ブランディング支援サービス」の一環としてSAKEX、米鶴酒造の3社で実証実験を行っているものです。
このサービスでは、企業がトークンを活用してブランドを強化し、新しい体験を提供できるよう、企画や技術面をトータルでサポートしています。
ーーー(編集部)本企画を実施するに至った経緯や背景などを教えてください



この取り組みは、今年1月にあった能登の震災で、SAKEXさんが「日本酒業界支援のNFT販売」に取り組んでいるのを知ったことがきっかけでした。
特にスピード感と、WEB3を活用した新しい支援方法に強く感銘を受け、「ぜひ一度お話ししてみたい」と考えいたところ、イベントで偶然SAKEXさんと出展が重なり、その場で直接お会いできたんです。そこで弊社から「何か新しい取り組みを一緒にやってみませんか?」と提案し、今回のプロジェクトが始まりました。
ーーー(編集部)今回の企画では①お酒のラベルトークン②体験チケットトークン③ファン証明トークンの合計3つのNFTが用意されているとのことですが、それぞれのNFTの役割や機能、そして複数のNFTを用意した意図などを教えてください



今回の企画では、購入者向けに3種類のNFTを用意し、それぞれが特別な役割と価値を提供するように設計されています。



お酒のラベルトークン
このトークンは、日本酒を購入した証明として機能します。購入されたお酒の情報が記録され、記念品としてもお楽しみいただけます。また、売上の一部が酒蔵への応援金として還元され、このラベルトークンを持つことで、購入者が酒蔵を支援している証明にもなります。
体験チケットトークン
こちらは特別イベントの参加チケットとして機能し、購入者がイベント当日に利用することで特別な体験に参加いただけます。
ファン証明トークン
実際に現地を訪れて体験した購入者に発行されるトークンです。このトークンを持っている方だけが利用できる場所や、特別な特典やメリットを今後用意する予定で、何度もその場所や地域に足を運びたくなるきっかけを作っていきます。具体的には、高畠町を巡る特典が得られるなど、地域の回遊を楽しんでいただける工夫も進めていく予定です。





このように、複数のNFTを用意することで、購入から体験、さらにその後の継続的なつながりまで段階的な価値を提供できるようにしています。
ーーー(編集部)山形県高畠町を訪問することで特典が発生するとのことですが、NFTの認証に関してはどのようなオペレーションを想定しているのでしょうか?



NFTの認証については、現地でのスムーズな確認ができるようにQRコード認証を採用しています。特典対象の方には、体験場所に設置したQRコードをスマートフォンで読み取っていただき、弊社のWeb画面にアクセスしてもらいます。
このWeb画面で特別体験トークンの保有状況を確認でき、確認が取れた方にはその場で「ファン証明トークン」を発行する流れです。この方法で、現地での操作もシンプルにし、ユーザーにとってもわかりやすいオペレーションを実現しています。
WEB3を意識させないシンプルな設計に
ーーー(編集部)企画設計をするにあたって意識したポイントなどがあれば教えてください





企画設計では、WEB3技術を活用しつつも、内容をシンプルにして分かりやすさを重視しました。特に、日本酒と現地での特別体験にフォーカスし、WEB3に詳しくない方でも「日本酒の魅力や山形の酒蔵体験を楽しめる」ように意識しています。



また、単なるオンラインの体験で終わらせず、現地での体験を通じて、酒蔵とのつながりが感じられるような仕組みにすることも重要なポイントです。
ーーー(編集部)想定ユーザーとしてはWEB3に理解のある層、米鶴酒造が好きな層のどちらを想定されていたのでしょうか?



想定ユーザーとしては、WEB3に詳しい層だけでなく、日本酒が好きな方全般を対象にしています。特に、米鶴酒造をすでにご存知のファンの方には、今回の特別体験をきっかけに、さらにコアなファンになってもらえればと考えています。
また、まだ米鶴酒造を知らない方でも、興味を持っていただき、現地の体験を通じてファンになってもらえるよう意識しました。
ーーー(編集部)マーケティングに関して、特にWEB3やNFTに精通していないユーザに対して、どのようなアプローチ方法を実施しましたか?



WEB3やNFTといった専門的な技術の説明にはあえて重きを置かず、「特別な体験ができること」や「特別なデジタルアイテムが得られること」にフォーカスして訴求しました。たとえば、「このイベントに参加すると、現地でしか手に入らない価値が得られる」という具体的なイメージを伝えるよう心がけました。



さらに、オンラインだけでなく実際の日本酒イベントや試飲会で対面で説明する機会を活用しました。特に。米鶴酒造さんが出展するイベントでは直接コミュニケーションを取り、興味を持っていただける方に丁寧に説明しました。
また、山形県高畠町の観光スポットや駅などにはポスターやチラシを設置し、地元の方々や訪問者にもアプローチしました。その他にも、東京のアンテナショップにも案内を置くなど、多様な接点を意識した広報活動を行いました。
ーーー(編集部)NFTの発行や特別体験の企画販売を進める中で、技術的な課題やコミュニケーションの問題があれば教えてください



弊社はこれまで日本酒の取り扱いやECサイトの運営経験がなかったため、販売に関する課題がいくつかありました。特に、購入者がスムーズにNFTを利用できるような仕組みづくりや、わかりやすい導線を整えることに時間を要しました。
しかし、SAKEXさんとの協力により、これらの課題を乗り越え、安心して購入いただける環境を構築することができました。
ーーー(編集部)山形での特別体験の販売実績を教えてください!



お陰様で特別体験企画を2回開催したのですが、どちらも完売いたしました。ご参加された皆様ありがとうございました!
ーーー(編集部)SAKEXさんの日本酒NFTに関しての販売状況はいかがでしょうか?



現在、弊社の「推し酒コレクション」のNFTは好調に推移しています。具体的には、日本酒の販売本数が250本を超え、オーナー数は80名以上となっています。特に、30本以上を購入いただいているリピーターもおり、ご満足いただいていると感じています。他の日本酒とNFTを掛け合わせたサービスの中でも、日本一の販売実績を誇っており、ブロックチェーン技術のおかげで販売数が透明性をもって公開されている点も好評です。



また、「推し酒コレクション」について一点ご説明したいのが、弊社が販売しているのはNFTそのものではなく、厳選された日本酒だという点です。お客様が日本酒をご購入いただいた際、その証として転売不可能なNFTをお渡しするという独自の仕組みを導入しています。この仕組みによって、NFTはあくまで購入の証明と記念品としての役割を果たしており、日本酒の購入体験に特別な価値を加えています。
ーーー(編集部)購入者の属性などを教えていただきたいです。
-scaled-e1734592996697-1024x891.jpg)
-scaled-e1734592996697-1024x891.jpg)



購入者は年齢層も幅広く、WEB3に詳しい方から日本酒愛好家の方まで、多様な方々にご利用いただいています。ブロックチェーンや暗号資産の知識がなくても購入できる仕組みを取り入れたことで、WEB3未経験の方にも安心してご利用いただけています。
「Made in Japan」の価値を国内外へ広める
ーーー(編集部)企画自体は現在進行系で実施されていると思うのですが、実施に事業を行っている中での気づき、感じていることなどがあれば教えてください。





実施している中で感じたのは、toC向けのプロモーションや認知度向上の難しさです。WEB3やNFTの認知が一般にはまだ十分広がっておらず、ウォレットの使い方やWEB3の仕組みそのものを説明する必要がある場面も多いと感じています。
その一方で、現地体験や対面でのアプローチでは、技術的な知識に頼らず興味を持っていただける機会が増えることも実感しています。課題と可能性の両方を意識しながら、進めていくことの重要性を再認識しました。
ーーー(編集部)今回の事業は貴社の「トークン活用型ブランディング支援サービス」の1事業としての取り組みだと思うのですが、今後日本酒以外で、どのようなジャンルでの活用を想定していますか?



今後は、日本酒以外にも「Made in Japan」の製品や体験全般を対象にしていきたいと考えています。
特に、伝統工芸品や地域特有の文化、食文化など、日本でしか体験することのできない「コト消費」に注目しています。こうした製品や体験には、それを作り出した背景や作り手の想いが込められており、その価値をトークン化を通じて国内外に広めたいと考えています。日本独自の魅力を新しい形で発信し、特別な購買体験を提供していきたいと思っています。
ーーー(編集部)生産者とユーザーが直接つながることができる最大のメリットとして、貴社はどのようにお考えでしょうか?



生産者とユーザーが直接つながることで、双方にとって大きなメリットが生まれると考えています。
ユーザーにとっては、製品や体験の背景にあるストーリーや作り手の想いに直接触れることで、より深い満足感や愛着が得られます。一方、生産者にとっては、自分たちの製品や体験に共感してくれるロイヤルカスタマーを増やし、信頼関係を築くきっかけになります。
このようなつながりが生まれることで、単なる一回の取引に留まらず、継続的な関係性が構築され、生産者の活動を長期的に支える仕組みが生まれると期待しています。


ーーー(編集部)最後に宣伝やPRがありましたら、お願いいたします。



弊社の「トークン活用型ブランディング支援サービス」は、製品や体験の魅力をトークン化し、その価値をより広く、的確に届けるためのサポートを行うサービスです。今回の実証実験を通じて、日本酒や体験型トークンの可能性を実感していただけたかと思いますが、今後は伝統工芸品や地域の特別な体験など、幅広いジャンルへの応用を視野に入れています。
「Made in Japan」の製品や体験には、多くの想いが込められており、それらを次世代の形で国内外に発信するお手伝いをさせていただきます。ぜひ、弊社サービスを活用して、唯一無二の魅力を多くの人々に届けていきましょう。



私たちは「日本酒に変革を」をミッションに掲げ、日本酒文化の未来を切り開く新しいビジネスモデルに挑戦しています。日本酒を軸に、地域や文化を活性化する取り組みを続けており、デジタル技術を活用して地域全体を盛り上げることを目指しています。
事業者や自治体の皆様とともに、新しい価値を創造し、日本酒と地域の新しい未来を築いていきたいと考えています。地方創生や地域活性化にご興味のある方は、ぜひご一緒にチャレンジさせてください!
ーーー(編集部)ありがとうございます!引き続きよろしくお願いいたします!

